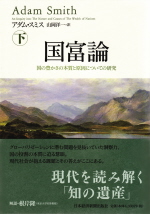後書きに代えて
山岡洋一
『国
富論』の翻訳を終えて
アダム・スミス著『国富論』は校正作業も終わり、3月下旬に日本経済新聞出版社から出版されることになった。そこで、翻訳の経緯を中心に、いくつかの点
について書いていきたい。

『国富論』を訳しはじめたきっかけは、直接には5年近く前の2002年秋に少し暇ができたことであった。たまたま、前の仕事が終わってから次の仕事の原稿
が届くまで、2か月ほどの期間があった。経済・経営の分野を中心に、主に時期ものの出版翻訳を行っているので、3か月以内に取りかかれない仕事を受けるこ
とはまずない。だから、たまにはひとつの仕事が終わった後、1か月や2か月の暇ができることがある。それまでは、そういう機会にやっておきたい中規模の課
題がいつも、いくつかあった。ところがこのときは、そうした課題がほぼ尽きていた。そこで、『国富論』を読みなおし、冒頭部分を少し訳してみようと考えた
のだ。
もちろん、何年ぶりかに暇ができたとき、『国富論』を対象に選んだのは偶然ではない。将来の可能性のひとつとしてではあるが、この本の翻訳をかなり本気
に考えるようになったのは、1980年代の前半だ。その時点の20年近くも前、産業翻訳をときおりやっていただけで、翻訳専業ですらなかったころだ。なぜ
翻訳なのか、なぜ『国富論』なのかはとても書ききれないので、要点だけ記しておこう。
失敗続きの人生で何かひとつ、大きな目標になるものはないかと考えていたとき、行き当たったのが『国富論』にかぎらず、古典の翻訳であった。なぜ翻訳か
というと、自分では満足できるものを書けるはずがないからだ。なぜ古典かというと、古典にはめったにないほど素晴らしい作品があるのだが、翻訳に問題が
あって、簡単には読めないものになっていると考えたからだ。数ある古典のなかではやがて、『国富論』の翻訳に取り組みたいと思うようになったが、それは、
たったいまの世の中を知るうえで重要な本であり、とくに世の中の全体を知るうえで重要な本なのに、しっかりと読んだ人はめったにいないと思えるからだ。
このように考えはじめたとき、『国富論』などの古典の翻訳は、不可能というほど非現実的な目標ではなかったが、それでも、簡単には実現しないほど難しい
目標であった。『国富論』を翻訳すること自体は、極端に難しいわけではない。趣味として訳していくのであれば、ほんとうに難しいのはそれだけの時間がとれ
るかだけだったと思う。だが、目標にしたのは古典を翻訳することだけではない。出版され、ある程度は世間に受け入れられるようにすることだった。1980
年代にこれがいかに難しい目標だったかは、いまでは簡単には想像できないかもしない。当時、フリーの翻訳者に道が開かれていたのは、産業翻訳を除けば、出
版翻訳のうちエンターテインメント小説など、一部の分野だけであった。『国富論』につながりそうなのは経済関係の出版翻訳だが、この分野は一般読者向けの
手軽な読み物であっても学者か評論家が訳すことになっていた。翻訳者という以外に肩書のない人間が入り込む余地などないように思えたのである。まして、古
典の翻訳であれば、一流の学者だけが取り組める領域のように思えた。
たとえば当時、『国富論』には大河内一男監訳、大内兵衛・松川七郎訳、竹内謙二訳などがあったが、どの訳者も一流の経済学者である。だが、一流の経済学
者が訳したから一流の翻訳だとはかぎらない。そして、ほんとうに納得できる訳があれば、自分で翻訳しようなどとは考えない。こうした大学者の翻訳には何か
共通した問題があり、自分なら別の視点からもっと優れた翻訳ができる、そういう大それた感想をもっていたから、古典の翻訳にいつか取り組みたいと考えてい
た。だが、そのためには、古典翻訳は大学者の領域だという見方をくつがえさなければならないし、その前に、経済分野では軽い読み物であっても学者か評論家
が訳すものだという見方をくつがえさなければならなかった。
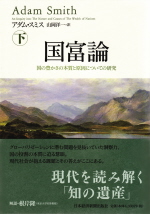
だから、1980年代前半には、『国富論』の翻訳という目標は、いってみれば、はるか遠くに見える山に登ってみたいという希望のようなものであった。麓
までたどりつくだけでも大仕事だと思えたのである。
1980年代後半はほぼ、産業翻訳で実績を積むことに費やした。1990年代はほぼ、出版翻訳で実績を積むことに費やした。その間にも、古典翻訳、とく
に『国富論』の翻訳を目標にしていたので、いつも、目標に近づく道を探していた。翻訳作業のなかでは、翻訳の質を高めて、大学者の訳に対抗できるようにす
る方法を探った。翻訳作業から少し離れたところでは、たとえば辞書を編集しようとした。当時はまだ、辞書にない訳語を使うのは「意訳」とされ、ある意味で
禁忌とされていたので、思いどおりの訳語を使うには、新しい辞書を作るしかないと考えたからだ。この「翻訳通信」を発行してきたのも、古典翻訳という目標
に近づくために役立たないかと考えたからだ。第1期は1994年にはじめて58号まであり、現在の第2期は2002年にはじめて、今回で58号になる。こ
こで記事を執筆するなかで、それまでの翻訳のどこに問題があり、どうすれば新しいスタイルの翻訳が可能になるかを考えてきた。
こうした道のりは試行錯誤の繰り返しだったといいたいところだが、実感としては錯誤錯誤の繰り返しだったように思える。しばらく歩んで行き詰まり、元に
戻るという動きを繰り返してきたのだ。だが、その間に世の中は着実に変化していた。たとえば長谷川宏のヘーゲル訳が受け入れられたし、経済分野でも、少な
くとも一般読者向けの本はフリーの翻訳者が訳すのがごく普通になっていた。たぶん、ひとりの人間が必要だと感じることは、何十万人、何百万人の人が必要性
を感じていて、それを満たすための動きが自然に起こるものなのだろう。
そして21世紀に入ったころには、五里霧中と思えていたなかで、気づいてみれば、はるか遠くにあったはずの山が目の前に迫っていたような状況になってい
た。2002年秋に少し暇ができたとき、もはや麓への道を探す必要はなくなっていた。麓近くにいつの間にか到着していたのだ。そこで、試しに少し登ってみ
ようかと考えたわけだ。
☆ ☆ ☆
2002年秋に『国富論』を少し訳しはじめたとき、通常とは違う方法をいくつかとっている。
まず、フリーの翻訳者なら受注してから翻訳をはじめるのが当然なのだが、このときだけは出版社と相談しないまま、翻訳をはじめた。この時点には、世の中
がフリーの翻訳者の古典翻訳を受け入れてくれるかどうか、まだ確信がもてなかった。世の中に受け入れてもらうには、第1関門として、出版社の編集者に受け
入れてもらえなければならない。編集者はどう反応するだろうか。
別の問題として、『国富論』の翻訳をはじめたとして、いつ終わるかの目処がまったく立たなかったという事情がある。かなりの時間がかかるのは確かだし、
翻訳以外に生計の手段がまったくないのだから、当面の生活を支えるための仕事で何度も中断するのは目に見えていた(実際にも、何度も中断した)。いつ終わ
るのか分からない仕事では、編集者と相談することもできない。そこで、フリーの翻訳者にはあるまじきことだが、出版の約束がないまま、翻訳をはじめること
にしたのだ。
もうひとつ、それまでとは大きく違う方法をとり、批評会、メーリング・リストなどを使って、何人もの方と議論しながら翻訳を進めることにした。
翻訳は通常、孤独な作業だ。もちろん、担当編集者とは議論や相談ができるのだが、実際にはいろいろな問題がある。最大の問題は編集者が忙しすぎること
だ。翻訳者が相談したい時期は、翻訳に取りかかって間もないころであるのが普通だろうが、そのとき、編集者は別の本で忙殺されている。編集者が相談にのっ
てくれるのは通常、翻訳原稿が完成してゲラができてからだ。そのころには翻訳者の側はすでに別の本の翻訳に取りかかっていて、頭が一杯になっている。この
ズレは翻訳者の立場ではけっこう頭の痛い問題である。
また、編集者と翻訳者は社会的にみて、発注者と受注者の関係にある。編集者は出版社という組織の一員だし、フリーの翻訳者は組織に属していない。このた
め社会的にみれば、翻訳者は極端に弱い立場にある。対等の立場で議論するのは、じつのところ、そう簡単ではないこともある。
『国富論』の場合、出版社からの発注がないまま翻訳をはじめたので、自然な相談相手である担当編集者もいなかった。それに本の性格上、さまざまな人と議論
しながら翻訳を進めていくことが不可欠だと考えたので、まずは批評会を開き、つぎにメーリング・リストで議論できるようにした。ページ数で全体の約4分の
1にあたる第1編の翻訳が終わった段階で、「評価版」と銘打った冊子を作り、多数の方に読んでいただいき、コメントをいただいた。この過程で翻訳者や編集
者、英語や経済の専門家、学生、一般読者など、さまざまな方からさまざまな点を学ぶことができた。教師と受講生、担当編集者と翻訳者といった社会的な関係
のない状況で議論できたことが大きかったのだと思う。
とくに大きかったのは、『国富論』が経済学についての専門知識をもたない読者向けに書かれた本であることをはっきりとつかめたことだろう。『国富論』は
経済学の源流だといわれており、経済学という分野はこの本からはじまったといってもいいほどなので、当時、経済学についての専門知識をもつ読者がほとんど
いなかったのはたしかだ。だから、『国富論』が専門書のスタイルで書かれていないのは当然のことなのだが、この点は意外と意識されにくい。後に経済学が学
問として確立するようになると、専門用語が作られ、定義され、ひとつの概念にはひとつの語が使われるようになっていくのだが、『国富論』ではまだ部分的に
しかそうなっていない。同義語に自由に言い換えていることが多い。言い換えにすぎない語のそれぞれに違った訳語をあてていると、訳文の意味が理解しづらく
なりかねない。
たとえば、stockとcapitalという2つの語はほとんどの部分で区別なく使われている。同義語として、自由に言い換えているのだ。ところが、こ
の2つの語のそれぞれを定義し、区別して使っている部分もある。経済学の専門家なら、一語一義が暗黙の前提になっているのだろうが、アダム・スミスはそこ
まで徹底していない。たしかに語を定義して使っていることもあるが、一語多義、多語一義になっている部分も多い。したがって、原文の語と訳語との一対一対
応を追求する翻訳スタイルでは、『国富論』を訳せないことが痛感できた。
このように、『国富論』の翻訳にあたって多数の方と議論できたことは、翻訳の質を高めるうえで、大きな意味をもった。もちろん、最終的に訳文を決めたの
は訳者であり、訳文に対しては訳者が責任を負っている。
以上のような形で多数の方と議論しながら翻訳を進め、その過程で考えた点を「翻訳通信」で紹介していったことから、思わぬ反応があった。批評会やメーリ
ング・リストには何人かの編集者も参加していて、それぞれ自社での出版を検討してくださったし、それ以外にも十指にあまる出版社が声をかけてくださった。
もちろん、出版をお願いできるのは1社だけなので、翻訳が一応完成した2005年秋になって、当初から積極的に議論に参加されていた編集者に出版をお願い
することにした。それ以外の出版社の編集者には、お世話になりながらお断りをしなければならなくなったわけだ。
だが、このように多数の出版社に声をかけていただいたことで、フリーの翻訳者による『国富論』の翻訳が世間に受け入れられる可能性があると自信をもつこ
とができた。編集者は読者の動向に敏感だから、読者に受け入れられる可能性がない企画に関心をもつはずがない。もちろん、編集者も翻訳者も自信をもってい
た本が売れなかった例は山ほどあるので、出版された後でなければ、読者に受け入れられるかどうかは分からない。だが、受け入れられる可能性はあるといえ
る。だから、編集者の反応は大きな励ましになった。何回もの中断をはさみながらも、最後まで翻訳をつづけることができたのは、この励ましがあったからだと
いえる。
☆ ☆ ☆
批評会などで多数の方と既訳について議論を重ねた結果、既訳のほぼすべてに共通する問題点も確認できたように思える。
『国富論』をめぐっては、これまで何回か、翻訳の質が議論されたことがある。代表的なものに竹内謙二著『誤訳−大学教授の頭の程』(有紀書房、1964
年)がある。これは、竹内謙二が自らの「正訳」と比較しながら、大内訳、大内・松川訳、水田洋訳などの誤訳を指摘した本だ。題名が刺激的なこともあって、
大きな話題になった。
だが、その竹内訳も含めて、各種の訳を多数の方と検討していくと、誤訳か正訳かに止まらない大きな問題があることが確認できた。それは、翻訳のスタイル
という問題である。竹内謙二訳から、大内兵衛訳、大河内一男監訳を経て、最新の水田洋監訳・杉山忠平訳(2000〜2002年)まで、どの翻訳にも基本的
に同じスタイルが使われている。原文の語と訳語の一対一対応を理想とする翻訳調のスタイルである。このスタイルは竹内訳が登場した大正時代には合理的だっ
たのだろうが、21世紀に入った現在では合理性を失っていると思える。
アダム・スミスは『国富論』の第3編第2章で、「法律はいったん作られると、そのときに背景になった状況、その法律が合理的であるために不可欠な状況が
なくなった後も、長く効力をもちつづけることが少なくない」と述べている。同じことがおそらく、翻訳のスタイルにもいえる。大正の時代にはまだ、欧米はは
るかに遠く、理解することなどとてもできないように思えたはずだ。欧米の進んだ思想や理論を日本語で表現することもできないように思えたはずだ。だから、
翻訳は原書を読む人のための参考資料だとされていた。原書を読み解くためであれば、一対一対応の翻訳調で訳していくのが合理的だ。このスタイルが「合理的
であるために不可欠な状況」は、21世紀の現在、なくなったといってもいい。だから、翻訳の新しいスタイルが必要になっている。
いま必要とされているのは、新しい翻訳ではない。新しいスタイルの翻訳なのだ。既訳では古い言葉が使われているから、いまの言葉で訳しなおす必要がある
という人がいるが、そうではないと思う。古い言葉であっても、使う必要があれば使えばいい。使えば言葉は新しい生命をもつようになるし、使わなければ生命
を失っていく。いま必要とされているのは、原書を読み解くための参考資料にするという目的のもとで合理的であったスタイルから脱却することだ。少なくとも
社会科学や人文科学など、論理を扱う分野ではそうだ。この点を『国富論』の既訳の検討のなかで再確認できたことで、専門家でも研究者でもない者、フリーの
翻訳者という以外に肩書のない者が『国富論』を訳す意味があるはずだという思いが強まった。
竹内訳から水田・杉山訳までの既訳は、原著を研究しようとする人を読者として想定していたように思える。少なくとも、そういう読者を暗黙のうちに想定し
なければ合理的だとはいえない翻訳スタイルが使われていた。今回の訳は、そういう読者を想定していない。もっと幅広い読者を想定している。アダム・スミス
がそうしたように、経済学についての専門知識をもたない読者を想定した。ただし、経済の動きに関心をもたない読者は想定していない。たったいまの世の中の
動き、とくに経済の動きに強い関心をもつ読者だけを想定している。そういう読者が、原著を読まなくても、原著者であるアダム・スミスが伝えようとした点を
理解できるようにすることが、今回の翻訳の目標である。この目標が達成できているかどうか、この目標を達成するために使った翻訳スタイルが受け入れられる
かどうかは、読者の判断を待つしかない。
☆ ☆ ☆
『国富論』の翻訳を目標にするようになってからでは25年近くが経過して、当初ははるか遠くに見えるにすぎなかった山に登りおえたように思える。たったひ
とつの目標を達成するのにこれほど長い年数がかかったのは、我ながら愚鈍としかいいようがないが、虚仮の一念という言葉もある。虚仮の一念で何ができたか
をみていただければ幸いである。
なお、アダム・スミス著山岡洋一訳『国富論』は3月23日に日本経済新聞出版社から出版されます。上下2巻で、上巻はA5版448ページ、定価
3,600円+消費税、下巻はA5版608ページ、定価4,000円+消費税です。
(2007年3月号)